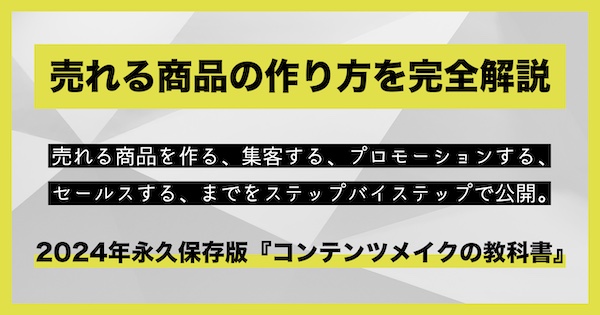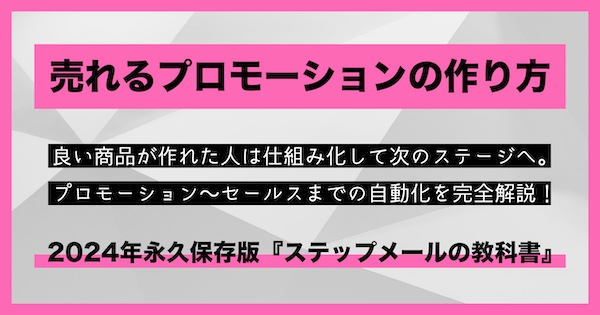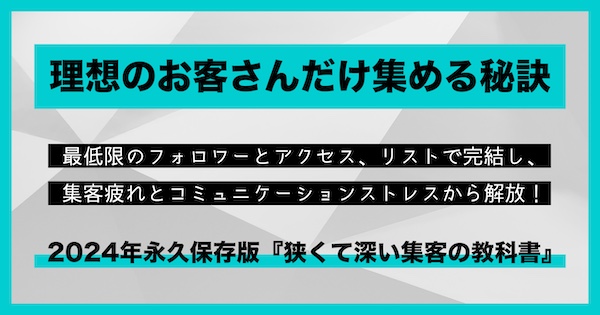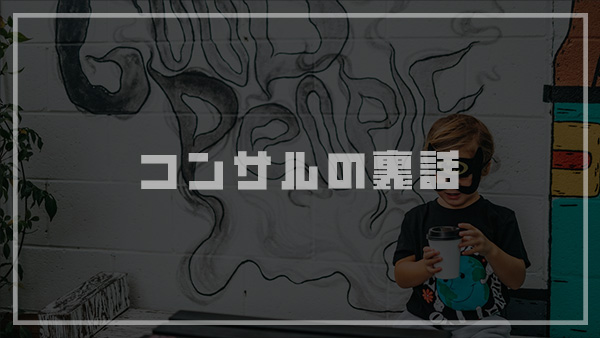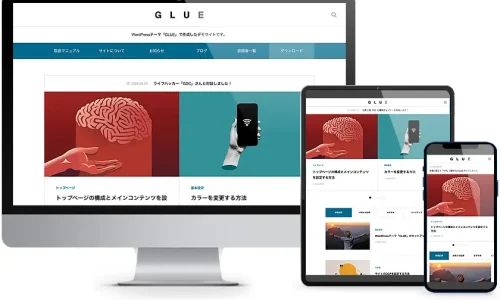こんにちは、服部(@FACTDEAL)です。
先日、年間通してアクセスが極小のゴミ記事を200記事ほど削除しまして。
まだまだゴミが記事ありそうな気もするんですが、確認作業だけでもけっこう時間がかかりそうなので、ボチボチやっていこうかなと思っています。
で、削除したからには新しい記事も増やしていかねばなと。
たまにリライトもするんですが、僕のブログ記事は情報網羅系ではなく「切り口ありき」なので、過去の古い記事が今需要があるとは思えないんですよね。
僕が見て「古いな」とか「内容薄いな」と思うものはバッサリ削除する派でして。
基本的にはネタも尽きることはないので、全体の記事数を増やすことを目的とするよりも、全体の記事数は減っても役に立つ記事が増えるようにしていきたいなと思うわけです。
Googleに向けて書いているわけではなく、読者さんに向けて書いているので。
で、「ネタが尽きない」という話をすると羨ましがられるんですが、これってセンスとか才能ではなくてテクニックの話なんですよね。
もちろん、人それぞれ使っているテクニックは違うとは思いますし、向いているテクニック向いていないテクニックというのがあるので、自分に合ったテクニックを身につける必要があるんですが。
今回はそういったテクニックをいくつか紹介していこうかなと思うんですが、きっかけは最近見かけたこの記事ですね。
ここで紹介されているテクニックの中で僕も使っているものもありますが、できるだけ被らないように僕なりの「ブログの記事ネタを無尽蔵に生み出す方法」をお伝えしていきますね。
ちょっと違った視点というか切り口を楽しんでいただければ。
ちなみに、お気づきかもしれませんが、この記事自体が「他人が書いている記事と同じテーマで自分の切り口で書く」というテクニックの1つを使って書かれていたりします。
1.配信日とテーマを設定する
ネタと関係ないと思うかもしれませんが、締め切りとテーマを設けるのはネタを尽きさせないためにはけっこう重要なんですよね。
なぜかというと、記事を書く日やテーマが決まっていないとインプットの感度が鈍るからです。
ブログを書くためにはネタを準備することが必要なのと同じように、ネタを準備するためにまずはネタを仕入れることができる状態にしておかなければならないということです。
準備の準備とでも言いましょうか。
例えば、「レンジローバーが欲しい」と思ったら、街を歩いていても車運転をしていてもレンジローバーばかりが目に入るじゃないですか。
でも、意識していないと全く目に入りません。
これと同じように、「3日後はカメラの記事を書こうかな」と配信日とテーマを決めることで、それに関する情報を能動的に収集するようになりますが、これが一切決まっていないと「あー、今日もネタが転がっていなかったな」で終わるわけです。
そうならないように、締め切りとテーマを最初に設定しましょう。
僕の場合は、週2回定日定時に配信しているコンサルnoteですかね。
強制的にアウトプットの日時とテーマを設定することで、インプットのためのアンテナを張っているということですね。
2.ツイートした内容を編集・加工する
これは、普段から僕がめちゃくちゃ活用している方法です。
ただ、たまに見かける「ツイートを埋め込んでひとこと添えて終わり」みたいな薄っぺらい記事を書くわけではなく、あくまでツイートを元に肉付けをするということです。
ツイートを埋込むのは全然ありなんですが、それがメインになってしまうと読みにくいですしコンテンツとしての評価もビミョーになりますからね。
具体的な方法に関しては、下記の3記事を読んでもらうとわかりやすいかなと思います。
ブログ ⇄ Twitterの活用法はいろいろあります。
3.複数のブログを立ち上げる
ネタが切れる理由の一つに、「ネタが無いのではなく、思いついたネタが今のブログのテーマに沿わないからボツにする」というパターンがあるんですね。
これでボツにするのって、普通にもったいないです。
おそらく、「いや、自分のビジネスに関係ないネタをブログに書いても読者が離れるでしょ」という論理だと思うんですが、この制約条件を排除するための解は至極シンプルで、「じゃぁ、別のブログで書けば良い」ということに尽きます。
なぜなら、今のビジネスや専門性とはズレるというだけで、「〇〇というネタで記事が書ける」ということは、誰かの役に立てる可能性があるからです。
ビジネスは1つのことだけをしなければならないというルールはないですし、ブログに関しても自分が持ちうる最も専門性の高い情報だけを発信しなければならないというルールはありません。
もっと言うと、自分が持ちうる最も専門性の高い情報と市場のニーズがマッチしなければビジネスは成立しないですし、逆に、自分の中でさほど高くない専門性でも市場のニーズとマッチすればそちらの方がビジネスの柱になる可能性が十分にあるということです。
なので、今のビジネスや情報発信のテーマにそぐわないから、そんなに大した情報レベルではないからといって安易にネタを切り捨てないようにしましょう。
それは、ビジネスチャンスをみすみす潰してしまっている可能性があるので、それであれば、新しいブログを立ち上げてそちらに記事を投下していきましょう。
もちろん、雑記ブログであればカテゴリーを分けて記事を蓄積していき、メインテーマとは外れるけど反応が高くなてきた記事に関しては、新しいブログを立ち上げて丸ごと移行するという方法もありです。
実際、僕は、メインブログと親和性の高いコンサルnoteをはじめとして、複数のブログを書き分けています。
4.構成の途中から書き始める
この記事の中で『CREMAの法則』の話をしていて、カンペもダウンロードできるようにしているので、まずはCREMAの構成を見てください。
①結論
②理由
③根拠
④手段
⑤行動
という構成になっているわけですが、ほとんどの人が「何を書こう?」と考えてネタ探しするときの視点は「①結論」なんですね。
ただ、ブログというのは、必ずしも結論を決めてから書き始めなければならないという流れは無く、「②理由」や「③根拠」から書き始めても良いんですね。
もし「②理由」がネタ元になる場合、例えば「このヘッドホンは壊れやすい(理由)」がネタ元になり、「このヘッドホンは買ってはいけない(結論)」といった感じでブログが肉付けされていくわけです。
で、「③根拠」はというと、「普通に使っていたのに3日で故障したから」みたいな感じで。
言ってしまえば自分の経験(根拠)から書き始めて、理由や結論に結びつけていっても良いということです。
この構成を知っておくことで、ネタの切り口が少なくとも5パターン増えますよね。
いつも何気なくやっていること(手段)から、他の構成の要素が付加されていってブログができあがってしまうというパターンもあるでしょう。
5.アイキャッチ画像からネタを考える
これはけっこう特殊な方法なんですけど、ブログを書いてアップするときには大抵アイキャッチを挿れますよね。
で、基本的な流れというのは、「記事を書く → 小見出しをつける → タイトルをつける → アイキャッチを挿れる」なんですが、敢えてアイキャッチから決めるというのがこの方法です。
論理的、左脳派ではなく、想像力豊かな人、芸術脳、直感的、右脳派の人とかはけっこうオススメですよ。
例えば、こういったフリー素材のサイトがあります。
ランダムに画像を見ながらイマジネーションを膨らましていき、ピンときた画像を元に記事の内容を考えていくんですね。
大喜利でよくある「画像でひとこと」みたいな感じで考えてもらえればわかりやすいですかね。
例えば、この記事のアイキャッチでもある下記の画像なんてどうでしょう?
・情報発信をするときは糖分を多めに撮ろう!
・PCやスマホを触った手は雑菌に侵されている!
・ブロガーは食事中もスマホを手離すな!
・インスタ映えする料理を撮影するポイント!
・クロワッサンの正しい食べ方を知っていますか?
などなど、ジャンルやカテゴリー問わず1つの画像からイメージできるものはけっこうありますよね、
で、これに慣れてくると、街中を歩いているときに目にする看板や映像、景色などからもネタを導き出すことができるようになったりします。
かなり特殊ではありますが、自分に向いていると思った人はぜひ。
アウトプット力よりもインプット力
巷ではアウトプットを重視されがちですし、実際、重要ですが、コンサルタントやマーケター、情報発信者は、インプットを止めたりインプットの質を落とした時点で終わりです。
とはいえ、「本を読む」などのベタなインプットに偏りすぎてしまうと、情報自体にエッジが立たなくなり、あなたが発信する意味がなくなってしまうんですね。
独自の切り口や価値観で勝負できなければ、情報の網羅性で勝負するしかなくなり、非常にハードモードでのビジネスゲームになります。
じゃぁ、独自の切り口や価値観で情報発信するためのコツは何かというと、「独自のネタ探し法」や「独自のインプット法」を見つけることなんですね。
自分なりのネタ探しの方法を見つけるということです。
良いブログを書く人は「アウトプット力がスゴい」「独自のフィルターがスゴい」と思われがちですが、僕の見解は違っていて、むしろネタ探しやインプット力の独自性が優れているんですね。
芸人が芸人たる所以は、アウトプット力もさることながら、普通の人が見逃す日常を「ネタ」に転換してしまうこと、つまり「気づき」や「疑問」、「問い」 、あるいは「探究心」だったりするわけじゃないですか。
そこを拾えなければ、どれだけアウトプット力が優れていても、文字通り「ネタは尽きる」わけです。
他人の「ブログの記事ネタを無尽蔵に生み出す方法」を学んだら、ネタ探しのための準備(期日やテーマの設定など)をしっかりし、「独自のネタ探し法」や「独自のインプット法」を身につけていきましょう。
学び、実践し、オリジナルに昇華させる、何ごとも「守破離」ですね。