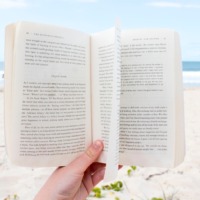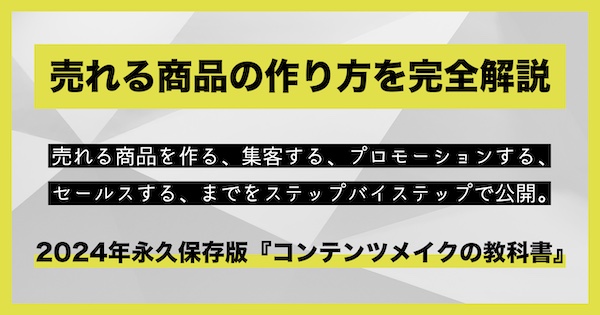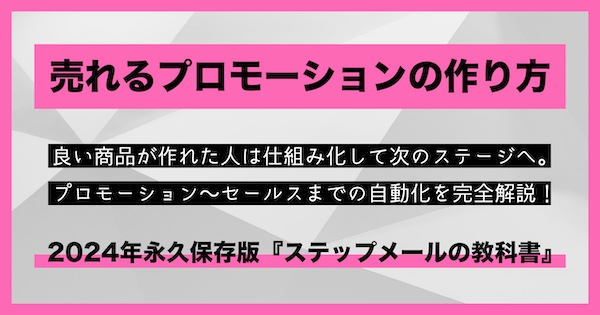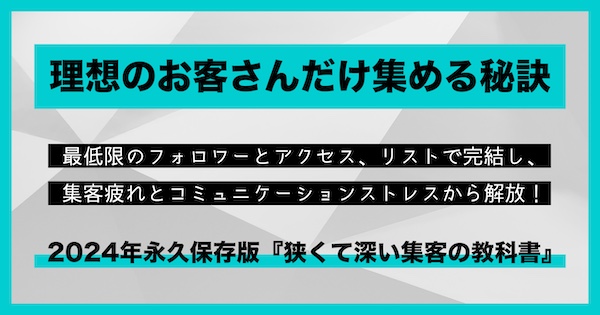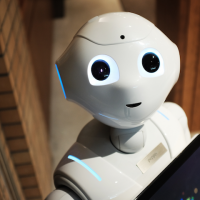最近は個人のブランディングについて聞かれることが多いんですが、ブランディングというのは、あくまでマーケティングの副産物です。
つまり、良いマーケティングを続けた結果、自動で形成されるのものだということですね。
逆に言えば、ある程度マーケティング(集客〜プロモーション〜セールス)を理解し、実践し、お客さんの反応を得られている人はブランディングを強化していくタイミングだと言えます。
ほったらかしにするより、戦略的にブランディングをしていく方が理想のお客さんが集まりやすくなりますし、ビジネスモデルも強固になるので。
副産物としてできあがったブランドを、これから大事に育てていくということですね。
❶マーケティング
👉息をするように相手の気持ちや良い未来を考えること❷ブランディング
👉①を続けた結果、大好きになってもらうこと❸ポジショニング
👉①②を踏まえて「〇〇といえば△△さんしかいない」と思ってもらうことビジネスも人生も全く同じなんですよね。https://t.co/ZyTjRJVlaf
— ハットリシンヤ|マーケとカメラとイロイロ (@FACTDEAL) April 19, 2020
なので、基本的にマーケティングの流れができた段階からブランディングはしていくべきなんですが、初期の段階でブランディングの進め方を一通り理解しておくことで「マーケティング ▶︎ ブランディング」の流れがスムーズになるので、頭に入れておくことを推奨します。
場合によってはマーケティングとブランディングを同時進行した方が良いフェーズもあるので。
ということで、今回はブランディングをする上で「最初にこれは押さえておいた方が良い」ということについて。
完全にマイナスブランディングになっている人、特にTwitterを見ていると「ああ、やっちゃってるなこの人」とう状況をよく目にするので、そういう人に届くとウレシイなと思います。
ブランディングに関してはこちらの記事も参考にしてください。
なんちゃってブランディング
ブランディングというのは、基本的に「お客さんに見てもらいたい姿」を形成することなんですが、TwitterやInstagramなどSNSの流行によって「凄そうに見せる」ことを優先する流れができてしまっているのが実情です。
収入アピールやフォロワー数など、実際にそれらの錯覚資産で多くの人を騙してマネタイズできてしまうので、一定の効果は確かにあるんですよね。
経歴詐称や詐欺など、お金持ちブランディングやセレブブランディングに失敗して、炎上して消えていく人が定期的に現れるのを見てもわかる通り。
Twitterでよく見る「〇〇社長」と名乗ったり、収入額や事業の数でマウントしたりしている人はほぼ同類か卵ですし、事業の実態や責任の所在、素性がわかっている人ならまだしも、それらが不透明な人は…ということですね。
で、こういったなんちゃってブランディングに乗っかったりマネをしたりするのは、情弱がガンガンを金をお落としてくれるので楽チンです。
すぐにリストやフォロワーも増えますし、集客もマネタイズも簡単にできてしまうでしょう。
一定の効果というのはそういうことです。
が、相手にするお客さんは依存体質かつクレーム資質を兼ね備えた情弱オンリーなので、そんなお客さんの相手をするためにブランディングをしたいかというと、おそらくみなさんそうではないと思うんですよ。
少なくとも僕のTwitterやブログを読んでくれている人に限っては。
他人と同じような「なんちゃってブランディング」で他人と同じような民度の低いお客さんを集めるのではなく、独自のコンテンツや価値観、人間性に魅力を感じてくれる自立心を持ったクレバーなお客さんに来てほしいですよね。
そう考えているのであれば、そういった金太郎飴ブランディングに安易に手を出すのはやめたほうが良いです。
もちろん、初動を作るためでもダメです。
人や自分を欺いたり、誰かの受け売りによるブランディングのリスクというのは、ビジネスを続ける限り永久についてまわりますから。
交流をリセットする
では、最初に何をすべきなのかというと、まずは上記のような特徴を持った胡散臭いブランディングの人たちとの交流を絶つことですね。
ここで大事なのは、それっぽいインフルエンサーが発信している情報に価値があるかどうかはどうでも良くて、それよりもその立ち位置に価値があるか、魅力的かどうか、独自性はあるかどうかを見るということです。
なぜなら、情報に関しては当たり前のマインド論や自己啓発的な内容がほとんどなので、価値があるかないかと言われたら実際「ある」からです。
ただ、それらは全て古典的なビジネス書でインプットできるんですよ。
それこそスティーブン・コヴィー先生の7つの習慣の第三章くらいまでを読めば、ビジネスをする上でのマインドセットは99%身に付きます。
目的はあくまでブランディングなので、インプットのためやフォロワーを増やすために「凄そうな人」に絡んで、同類だと思われる時点でブランディングはマイナススタートになるんですね。
インプットは本でできるし、自分のブランディングのためのフォロワーは誰かのおこぼれをもらうのではなく、自分で集めなければ意味がありません。
そうでなければ、影響力のある人に媚びてブランディングができたとしても、フォロワーからすれば所詮その人の子分でしかないので、独自のブランドというのは生まれようがありません。
みんなありきたりなビジネス書とか劣化コピーの情報商材しか買わないし、ビジネス系の焼き回しYouTubeしか観ないから、小説読んだり、マンガ読んだり、歌詞見たり、映画観たりして価値観や世界観をパクって自分のビジネスに落とし込むだけで余裕で差別化できる。
あ、企業秘密言っちゃった。
— ハットリシンヤ|マーケとカメラとイロイロ (@FACTDEAL) December 3, 2020
なので、あらゆるインフルエンサーからビジネス的なインプットをしている人は、一旦リセットすることをオススメします。
また、その人の立ち位置や価値観に魅力を感じても「その人のようになりたい」と思ってしまっているのであればそれもアウトです。
それはもう思考停止と変わらないので。
あくまで自分は自分、その人にはなれないので、その人の価値観に共感した上で「じゃぁ、自分はどうなりたいのか」を考えることこそが独自のブランディングの土台になるんですね。
ブランディングのための交流は、上下関係(憧れ)ではなく、あくまで横並び(共感)のみで作るということです。
インプットパターンを変える
交流を整えたら次はインプット環境ですが、これは上記もツイートでも書いた通り、一般的なビジネスパーソンとは違う場所や人からインプットをするということが重要です。
ビジネスYouTubeではなく映画、ビジネス書ではなく小説やマンガ、セミナーに行くのではなく旅行に行くといった感じでですね。
もちろん、専門家として価値を提供するために知識を得たり、スキルを磨くために必要に応じてビジネス的なインプットをすることは必要ですが、それは当たり前というか大前提の話です。
ただ、ブランディングにおける差別化やオリジナリティのための要素はもうそんなところからは引っ張ってこれないんですよ。
それよりも、そこに自分の感性やクリエイティブな視点をどう掛け合わせるかということの方が大事で。
Twitterなどで新たな交流を作って絡む人に関しても同じです。
コンサルタントやマーケター、起業化ではなく、作家や写真家、映画監督、ミュージシャン、アスリートなどから学ぶ方が、圧倒的にオリジナリティは形成されていきますし、自分のリソースを掛け合わせることによって商品やサービスの付加価値も増えます。
業界の状況も把握しておく必要はあるので、フォローのバランスとしては、同業やビジネス系3割、それ以外7割くらいが良いですね。
ということで、今回はブランディングをする上で最初に押さえておいた方が良い点についてお伝えしましたが、ここさえ押さえられていれば、あとは下記のフェーズを固めていくだけです。
コンセプトを決める
プロフィールを整える
見た目を整える
メディアを選定する
世界観を整える
言葉を整える
プロフィールを整える
セーブする情報を決める
フロントの境界線を引く
バックブランディングを考える
オンラインサロンやコンサルではこれらのアドバイスやサポートをしていますが、これらの内容は個々の状況によって内容は大きく変わってくるのでコンテンツにするのは難しいんですよね。
可能な部分に関してはコンテンツ化していこうかと思いますが、誰よりも早く地盤を固めておきたいなという人はMEDIA PRODUCEを活用してみてください。